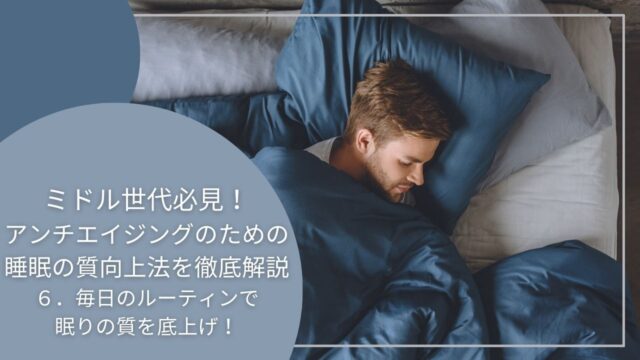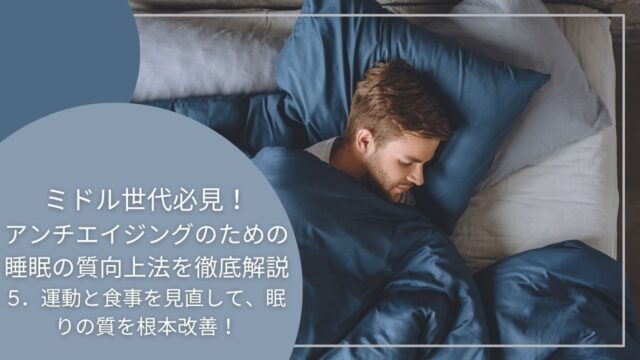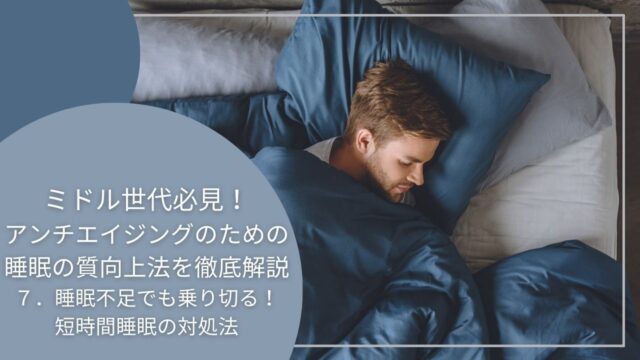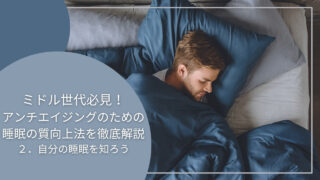ミドル世代必見!アンチエイジングのための睡眠の質向上法を徹底解説 1.睡眠不足の怖さを知ろう
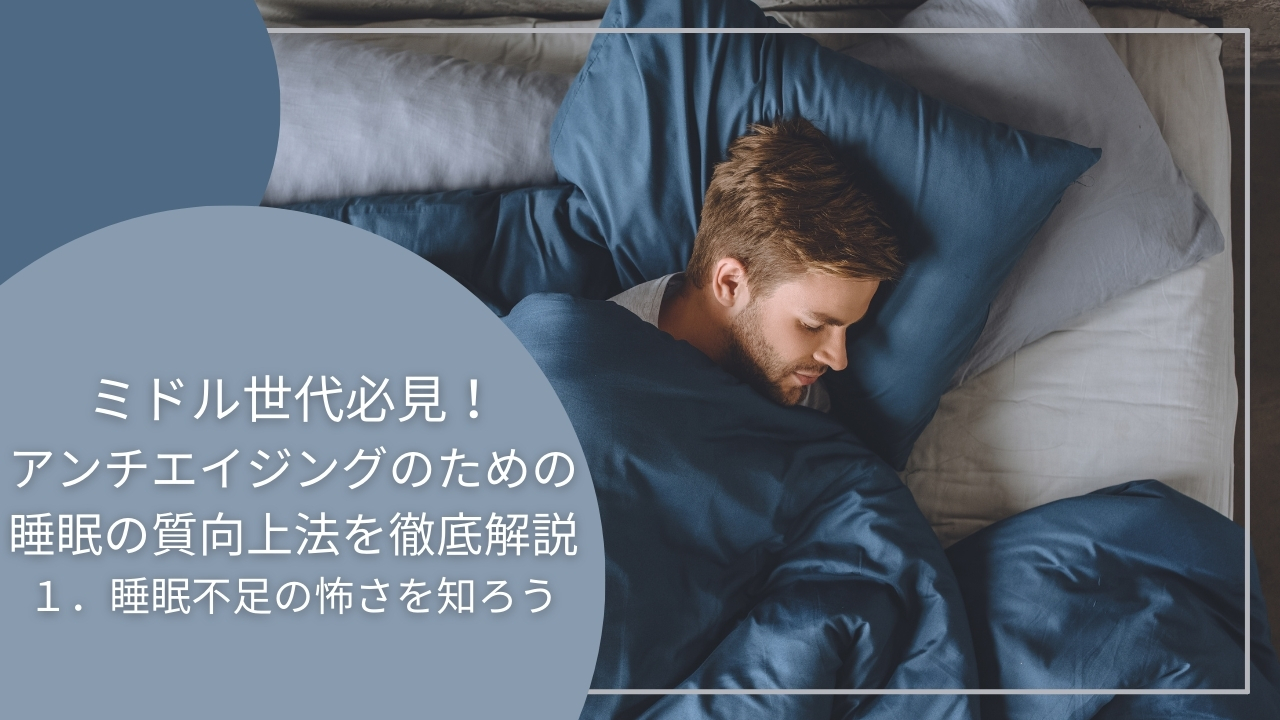
- 睡眠とアンチエイジングの関係はよく聞くけど、具体的になにが重要なの?
- 眠れてるけど、眠った感じがしないのをなんとかしたい
- 睡眠の質を改善して、日中のパフォーマンスを上げたい
- ベットに入ってもなかなか眠れない
- 睡眠が浅く、夜中に何度も目が覚める
アンチエイジングを考えるうえで、睡眠の質の向上は欠かせません。とはいえ、一言で「睡眠の質を向上させる」と言っても、その方法は多岐にわたり、人によって合う・合わないがあるのが現実です。
実際、私自身もなかなか自分に合う方法が分からず、枕やマットレスを変えたり、アロマや睡眠ガジェットを導入したり、さまざまな方法を試しましたが、すべてが効果的だったわけではありません。
そこで本記事では、「睡眠の質を向上させたい」と考えている方のために、私がこれまでに学び、実践してきたさまざまな手法を、体系的に紹介していきます。
この記事を読めば、自分に合った睡眠改善法を見つける手助けになるはずです。そして、質の良い睡眠を手に入れることで、ミドル世代からのアンチエイジングライフをより充実させることができるでしょう
私自身、睡眠の質を向上させるために、多くの書籍や研究論文を読み、実際に試してきました。その知識と経験をできる限り詰め込んでいますので、ぜひ最後まで読んでみてください。一緒に睡眠の質を高め、若々しく健やかな毎日を目指していきましょう!
また、記事の最後に参考にした書籍を掲載しておきますので、さらに深く学びたい方はチェックしてみてください。
まずは睡眠不足が我々の身体へ与える影響をまとめていきたいと思います。
目次
睡眠負債とは?40代から意識すべき眠りの借金

「睡眠負債」という言葉を聞いたことがありますか?これは、気づかないうちに溜まっていく“眠りの借金”のこと。長期間にわたる睡眠不足が積み重なることで、心身の健康に悪影響を及ぼす状態を指します。
この概念は、スタンフォード大学の睡眠医学研究者、ウィリアム・デメント博士によって提唱されました。「負債」という表現が使われるのは、借金と同じように、睡眠不足も少しずつ溜まっていき、やがて大きな問題を引き起こすからです。
特に40代以降は、仕事の責任が増し、家庭や社会での役割も大きくなる年代。無理をして睡眠を削りがちですが、実はそのツケは確実に溜まっていきます。しかも、残念ながら睡眠は「貯金」することができません。つまり、前もって寝だめをしておくことは不可能で、負債を返済するにはしっかりと質の良い睡眠をとるしかないのです。
各国の平均睡眠時間

- フランス:8.7時間
- アメリカ:7.5時間
- 日本:6.5時間
日本人の約40%が、1日の睡眠時間が6時間未満だと言われています。これは、アメリカの基準では「短時間睡眠」に分類される水準です。ミシガン大学が2016年に実施したインターネット調査によると、100カ国の中で日本の平均睡眠時間は最下位だったという結果が出ています。
しかし、実際には日本人の多くが「7.2時間ほど眠りたい」と感じており、理想と現実の間に大きなギャップがあるのが現状です。みなさんは、十分な睡眠を確保できていますか?
では、健康的に生きるための理想的な睡眠時間とはどれくらいなのでしょうか? 2010年に発表された「睡眠時間と寿命」に関する16件の論文を分析した系統的レビューによると、人間が最も長生きできる睡眠時間は「6〜8時間」と報告されています。
睡眠不足の悪影響

ではここから、睡眠不足が我々の身体へ与える悪影響を見ていきましょう。睡眠不足が我々の身体へ与える影響をまとめると
- マイクロスリープが起きる
- 寝る間を惜しむと寿命を削る
- 老化が進行する
- 免疫力を弱める
- 肥満になる
- 認知症リスクが拡大する
- 記憶の定着が悪くなる
- 不規則な睡眠は健康・美容の大敵
- 人間関係が悪化する
マイクロスリープが起こる

マイクロスリープとは、1〜10秒程度の短い眠りのことを指します。これは脳の防御反応として発生し、本人が気づかないことがほとんどです。
実際に、夜勤のある医師とない医師を対象にした実験では、タブレットにランダムに現れる丸いボタンを押すテストが行われました。その結果、夜勤のない医師は正確に反応できたのに対し、夜勤のある医師は数秒間ボタンに反応できない場面が見られたそうです。これはマイクロスリープが起こり、一時的に脳の認識機能が停止したためと考えられています。
特に恐ろしいのは、本人がまったく自覚しないまま数秒間意識を失ってしまうことです。例えば、時速60kmで車を運転中に4秒間のマイクロスリープが発生すると、車は約70mも無意識のまま暴走することになります。これは重大な事故につながりかねません。
日常生活の中でも、以下のような症状が見られたら要注意です。
- 会議中や授業中に、ふと意識が飛ぶことがある
- 読書中に同じ文章を何度も読んでしまう
- PCのタイピングミスが頻発する
このような状態が続く場合、15分程度の仮眠を取ることで改善することが多いです。ただし、仕事中などで仮眠が難しい場合は、1分間目を閉じて視覚情報を遮断し、脳を休めるだけでも、ある程度回復が期待できます。
寝る間を惜しむと寿命を削る

日本には、「寝る間を惜しんで働くことが美徳」という風潮がありますよね。上司より先に帰ることに引け目を感じたり、翌日までに仕上げなければならない資料に追われたり…。こうした経験をしたことがあるビジネスパーソンは多いのではないでしょうか?
しかし、実際には睡眠不足になると生産性は大幅に低下します。睡眠を軽視することは、決して効率的な選択ではなく、むしろ健康や仕事のパフォーマンスに悪影響を及ぼす「マイナスの選択」になりかねません。
日本人を対象にした調査によると、1日の睡眠時間と死亡率には明確な関係があることが分かっています。7時間睡眠の死亡率を1とすると、
- 4時間睡眠での死亡率1.6
- 10時間以上の睡眠での死亡率1.8
4時間以下の睡眠では、男女ともに非癌・非心血管疾患の死亡リスクが有意に上昇し、特に女性は冠動脈疾患による死亡リスクも高まることが分かっています。
また、意外にも10時間以上の長時間睡眠でも死亡率が高まることが報告されています。これは、循環器疾患による死亡リスクの上昇と関連があると考えられていますが、その原因はまだ完全には解明されていません。研究者の間では、長時間睡眠を取る人の中には、もともと健康状態が悪い人が多いのではないかという指摘もあります。
日本の平均寿命は男女ともに80歳を超え、世界トップクラスを誇ります。しかし、「健康寿命」(介護や医療に頼らず自立して生活できる期間)は、これより約10年も短いのが現状です。つまり、多くの人が人生の最後の10年間を、病気や体の不調を抱えながら過ごしていることになります。この点では、日本は他国と大きな差がないのです。こうした健康寿命の短縮には、睡眠不足も影響を及ぼしている可能性があります。
老化が進行する

私たちの身体は、睡眠中に全身の細胞を再生・修復しています。しかし、その過程で有害な老廃物も発生します。その中でも特に注意すべきなのが、「フリーラジカル(活性酸素)」です。
フリーラジカルは、体内の細胞を酸化させ、いわば「錆びつかせる」ことでダメージを与えます。これが蓄積すると、脳卒中や心血管疾患、糖尿病などの重篤な病気のリスクが高まるのです。
このフリーラジカルを抑えるうえで重要なのが、睡眠中に分泌される「メラトニン」です。メラトニンには強力な抗酸化作用があり、フリーラジカルを分解・無毒化して体外へ排出する働きがあります。
しかし、睡眠不足になるとメラトニンの分泌量が減少し、フリーラジカルを十分に除去できなくなるため、結果的に老化が加速してしまいます。
健康的に年齢を重ねるためには、質の良い睡眠を確保し、メラトニンの分泌を最大限に活かすことが重要です。
免疫機能を弱める

睡眠不足が続き、睡眠負債が蓄積すると、風邪などの感染症にかかりやすくなることが知られています。しかし、それだけではありません。睡眠不足は、体内の「ナチュラルキラー(NK)細胞」の活性を低下させ、がん細胞を排除する力を弱めてしまうのです。
人間の体内では、毎日約5,000個ものがん細胞が発生しているといわれています。本来、自然免疫が働くことで、これらのがん細胞は排除されます。しかし、睡眠不足が続くと免疫細胞の働きが鈍り、がん細胞を抑える力が低下してしまうのです。
この影響を裏付ける研究も報告されています。
- 東北大学が実施した40〜79歳の日本人女性2万人を対象とした調査では、平均睡眠時間が6時間以下のグループは、7〜8時間睡眠のグループと比較して乳がんのリスクが1.62倍に上昇。
- 同大学が男性2万人を7年間追跡した研究では、6時間以下の睡眠グループは、7〜8時間睡眠のグループと比べて、前立腺がんの発症リスクが2.08倍だったと報告。
これらの研究結果からも分かるように、睡眠不足はがんリスクを高める要因の一つです。
また、睡眠不足はワクチンの効き目にも悪影響を及ぼします。フランス国立衛生医学研究所を中心とした国際研究チームの報告によると、1日の睡眠時間が6時間未満の人は、ウイルス感染症のワクチン接種後の免疫反応(効果)が低下することが分かっています。
つまり、睡眠不足が続くと、以下のような悪循環に陥る可能性があります。
- 睡眠不足に陥る
- 免疫力低下
- ワクチンの効き目が弱まる
- 体調が悪化
さらに、2023年に北海道大学が行った研究では、睡眠不足の人ほど、免疫機能に欠かせない「αディフェンシン」という物質の分泌量が少ないことも報告されています。αディフェンシンは体内の防御機構の一部としてウイルスや細菌の侵入を防ぐ役割を果たしていますが、睡眠時間が不足すると、その分泌量が減ってしまうのです。
このメカニズムの詳細はまだ完全には解明されていませんが、睡眠不足が免疫機能を低下させることは、科学的にも明らかになりつつあります。
肥満になる

睡眠不足になると、太りやすくなることはよく知られています。では、睡眠不足が体内でどのような影響を及ぼすのでしょうか?
具体的には、次のような変化が起こります。
- レプチン(食欲を抑制するホルモン)の分泌が減少
- グレリン(食欲増進ホルモン)の分泌が増加
- コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌が増加
健康な状態では、コルチゾールの分泌量は早朝に最も高く、1日のリズムを作り、目覚めを促します。通常、夜になるとコルチゾールの分泌量は急激に減少し、ピーク時の10分の1以下まで落ちます。このように、コルチゾールは体内で重要な役割を果たしています。
適切に分泌されているコルチゾールは、次のような機能をサポートします。
- 強いストレスから心身を守る
- 糖代謝の調節
- 脂肪を分解し、エネルギー供給を促進する
- 血糖値の低下を防ぐ
ところが、睡眠不足により、コルチゾールの分泌が増加すると
- 脂肪の蓄積を促進
- 免疫力低下による感染症リスクの増加
- 血圧や血糖値、コレステロール値の上昇
- 精神疾患(うつ病、不眠症など)のリスク増加
さらに、レプチンの減少とグレリンの増加が相まって、次のような悪循環が始まります。
- 摂取カロリーが増える
- 内臓脂肪が増える
- 肥満のせいで睡眠時無呼吸が悪化
- 更に睡眠の質が悪くなる。
このように、睡眠不足が体重増加と睡眠の質の悪化を引き起こし、悪循環に陥ることがよくあります。
実際、アメリカで行われた研究では、健康な人を4時間睡眠グループと9時間睡眠グループに分けて、2週間の実験を行いました。その結果、4時間睡眠のグループでは、以下のような変化が見られました。
- レプチンの血中濃度が低下
- グレリンの血中濃度上昇
- カロリー摂取量 +308kca/日
- 体重+0.5kg
- 内臓脂肪量 +7.8cm3(11%増)
その後、4時間睡眠のグループが9時間睡眠を3日間とった結果、これらの変化は元に戻ったそうです。
また、シカゴ大学で行われた研究では、肥満気味の人を対象に、いつもより長く眠るグループと普段通りのグループに分けて実験が行われました。その結果、普段6.5時間未満の睡眠の人々が睡眠時間を増やすと食欲が落ち着いたことがわかりました。具体的には、睡眠時間が1時間増えるごとに、摂取カロリーが150kcal減少したとのことです。
これらの研究結果を見ると、睡眠不足はダイエットの大敵であり、体重管理には十分な睡眠が欠かせないことが分かります。
認知症のリスクが拡大する

睡眠不足になると、認知症のリスクが4倍に増加することがわかっています。特に、アルツハイマー型認知症では、脳内で神経細胞が死滅し、脳の萎縮が進行します。この過程で、脳内に老人斑というアミロイドβというタンパク質の塊が現れます。このアミロイドβが蓄積することで、認知症が進行すると考えられています。
睡眠中には、脳脊髄液が脳内に流れ込み、老廃物を除去する働きがあります。しかし、睡眠時間が十分でないとこのプロセスが適切に行われません。その結果、アミロイドβが脳内に蓄積しやすくなり、認知症のリスクが高まります。
アメリカのタウブ研究所が実施した65歳以上の非認知症者1041人を対象としたコホート研究では、睡眠不足が認知症のリスクを4倍に高めることが確認されています。
また、アメリカの国立アルコール乱用・依存症研究所による研究では、22〜72歳の健康な男女20人を対象に徹夜後の脳内アミロイドβ量を測定した結果、一晩の徹夜でもアミロイドβが5%増加することがわかりました。アミロイドβが脳内に溜まっていると、認知症のリスクだけでなく、以下のような精神的な問題も引き起こすことが分かっています。
- 疲れや不安が強くなる
- イライラしやすくなる
- 幸福感が弱まる
さらに、レム睡眠の不足も認知症を引き起こす可能性があります。オーストラリアのグループによる研究では、67歳平均の人々を対象にした調査で、睡眠中のレム睡眠の割合が1%減少するだけで、その後の12年間で認知症の発症リスクが9%増加することが確認されました。
筑波大学の林教授らによる研究でも、レム睡眠中に大脳皮質の毛細血管への赤血球の流入量が増加していることがわかりました。これは、脳に必要な酸素や栄養を供給し、二酸化炭素や不要物を回収するプロセスがレム睡眠中に活発に行われていることを示しています。レム睡眠が不足すると、このプロセスが十分に行われず、結果として認知症のリスクが高まると考えられています。
記憶の定着が悪くなる

テスト前などで一夜漬けで勉強した経験がある方も多いのではないでしょうか。しかし、残念ながら一夜漬けでは記憶が定着しません。それどころか、日中のパフォーマンスが著しく低下する可能性があります。徹夜明けの脳のパフォーマンスは、飲酒して酩酊している状態と同じくらい低下すると言われています。具体的には、ビールの中瓶を3本飲んだときと同程度の影響があるそうです。これでは、重要な会議の前日に徹夜で資料を作成しても、効果的にはなりませんよね。
当たり前のことですが、よく眠った人の方が効率は格段に良くなります。徹夜だけでなく、睡眠不足が続き睡眠負債が溜まるとやはりパフォーマンスは低下します。例えば、1日4時間の睡眠を6日間続けると、完全に徹夜したときと同程度の効率に落ちることがわかっています。また、1日6時間の睡眠では10日続けると、やはり徹夜と同程度の効率にまで低下します。
人は日中得た情報を睡眠中に処理し、長期記憶として定着させます。そのため、一夜漬けでは効果が薄いのです。記憶を定着させるためには、適切な睡眠時間と質が必要なのです。加えて、睡眠不足は注意力を散漫にさせ、良い結果を生むことはありません。
ちなみに、日本のトップ高校生は、意外にも睡眠時間が長いことがわかっています。例えば、一般的な高校生の平均睡眠時間は6時間程度ですが、筑波大学附属駒場高校の生徒は8時間の睡眠を確保しているそうです。
睡眠の質と量が、学業や仕事のパフォーマンスにどれほど大きな影響を与えるかは、皆さんも実感しているはずです。
不規則な睡眠は健康・美容の大敵

交代勤務などで睡眠が不規則になると、循環器疾患やうつ病を発症するリスクが高まります。これは、勤務スケジュールによる睡眠・覚醒リズムの乱れと、生体リズムのズレが原因です。睡眠時間のばらつきが120分以上、入眠時間のばらつきが90分以上になると、以下のようなリスクが増大します。
- 循環器疾患のリスクが2倍以上
- うつ病を発症するリスクが3倍
これらのリスクには、メラトニンの分泌量が大きく関与しています。メラトニンは夜間(おおよそ21時)に分泌が始まり、深夜3時頃にピークを迎えます。分泌量が増えると眠くなり、減少すると目が覚めるため、睡眠ホルモンとも呼ばれています。メラトニンには、血管を保護し、清潔に保つ働きもあります。血管に血栓ができるのを防ぎ、血圧を下げる作用があるため、メラトニンの十分な分泌がもたらす質の高い睡眠は、心血管疾患(心筋梗塞や脳梗塞など)のリスク低減に役立ちます。
しかし、交代勤務などで不規則な睡眠が続くと、メラトニンの分泌が不十分になり、循環器疾患のリスクが上昇する可能性があります。
また、不規則な睡眠は肌荒れを引き起こす原因にもなります。夜間に深い睡眠が取れないことで、成長ホルモンの分泌量が減少し、肌のサイクルが乱れます。成長ホルモンは、子どもの成長に必要なホルモンという印象がありますが、大人にとっても非常に重要です。このホルモンは肌の再生や修復、細胞の成長を促進し、成人における成長ホルモンの欠乏症は、以下のような症状を引き起こす可能性があります。
- 筋肉量の減少
- 体脂肪の増加
- 骨・脂質・血糖の異常
- 疲労感
- 集中力低下
- 抑うつ
成長ホルモンは、深睡眠中に最も多く分泌されます。良質な睡眠を確保することで、成長ホルモンの分泌が正常になり、以下のような効果が期待できます。
- 紫外線ダメージの回復
- 肌のバリア機能を保つ
- 新陳代謝の向上
これにより、若々しい肌や健康な体を保つことができます。睡眠の質を見直すことは、健康を維持するためにとても大切です。
人間関係が悪化する

睡眠不足は人間関係にもマイナスの影響があります。
- ちゃんと寝ないと不誠実になる
- ちゃんと寝ないと友達が減る
ということがわかっています。
ちゃんと寝ないと不誠実になる
バージニア工科大学の研究によると、睡眠不足になるほど意志力が低下し、他人を騙したり、誤魔化したりする傾向が強くなるそうです。また、シンガポールマネジメント大学の調査では、睡眠不足の社員が、そうでない社員よりも仕事中にネットサーフィンをする確率が高いことがわかっています。つまり、十分に睡眠を取らないと、やるべきことがあっても、周囲の誘惑に勝てず、目の前の欲求に流されやすくなるということです。
ちゃんと寝ないと友達が減る
2017年、スウェーデンのカロリンスカ研究所で行われた実験によると、人はぐっすり眠ると美しくなり、睡眠不足になると外見的な魅力が低下することがわかっています。数日間の睡眠不足でも人の魅力は減少することが確認されました。大学生の男女25人を対象にした実験では、
- 1回目:2日連続で十分な睡眠を取らせる
- 2回目:1回目の1週間後に、2日連続で4時間だけ睡眠を取らせる
- 1回目、2回目のあとにそれぞれの被験者の化粧をしていない顔の写真を撮影
という方法で、1回目と2回目の後にそれぞれの被験者の化粧をしていない顔写真を撮影。その写真を別の男女122人に見せて、次の5つの質問に対して評価を行いました
- どのくらい魅力を感じるか?
- 健康そうに見えるか?
- 眠そうに見えるか?
- 信頼できそうか?
- 交流したいか?
その結果、睡眠が十分に取れていない顔写真に対しては、
- 交流したいか?の評価が低い
- 魅力的に感じない
- 不健康そう
といった評価がされました。
また、カリフォルニア大学バークレー校のマシュー・ウォーカー教授の研究チームによる発表では、質の良い睡眠が取れなくなると、相手の表情を読み取る能力が低下することがわかっています。18人の健康な成人被験者を対象に、好意的な表情から敵対的な表情までの70種類の表情の画像を見せ、十分な睡眠を取った状態と睡眠不足の状態でそれぞれ実験を行いました。睡眠不足のとき、脳の感情を読み取る部分である島皮質前部と前帯状皮質の活動が低下し、画像の表情が好意的か敵対的かを区別できなかったそうです。つまり、睡眠不足のとき、人は相手が好意的な表情をしていても、「自分を敵視している」と誤認してしまう傾向があることが明らかになっています。
睡眠負債を返せばパフォーマンスはあがる

ここまで見てきたように、睡眠不足が私たちの体に及ぼす悪影響は非常に大きいことがわかったかと思います。しかし、裏を返せば、睡眠負債を返済することでパフォーマンスが向上するということも意味しています。
例えば、バスケットボール選手10人を対象に行った実験があります。実験では、40日間毎晩10時にベッドに入るようにしてもらいました。フリースローの成功率は最初は変わりませんでしたが、2週間目、4週間目と経過するうちに、フリースローは0.9本、スリーポイントシュートは1.4本も多く決まるようになったそうです。また、選手自身もものすごく調子が良くなったと実感したという結果でした。
この実験からわかることは、睡眠負債を返すことでパフォーマンスが向上するということです。では、週末にたくさん寝ることで睡眠負債を返済できるのでしょうか?
健康な10人を対象に、14時間ベッドに入るという実験が行われました。実験前の平均睡眠時間が7.5時間だった参加者は、1日目と2日目に13時間近く眠り、3週間後には平均8.2時間に固定されました。この8.2時間は、実験参加者が生理的に必要とする正常な睡眠時間ということになります。つまり、平均睡眠時間が7.5時間だった人たちは、毎日40分の睡眠負債を抱えていたことになります。この負債を返済するのに3週間かかったということは、週末にたくさん寝る程度では、睡眠負債は十分に返済できないということです。
したがって、普段から睡眠の質を向上させることが非常に大切だということがわかります。
次回は、自分の睡眠について知る方法をお伝えしていきたいと思います。